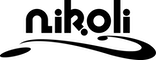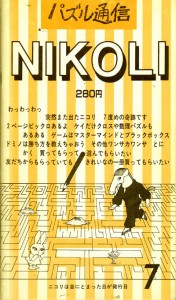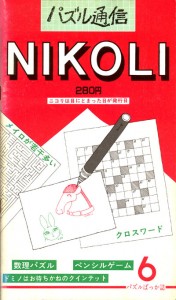
1982年は6号(60ページ、280円)、7号(64ページ、280円)、8号(60ページ、280円)の3冊を出している。
私は自動車免許を持っていず、歩いての配本期間はなんと3週間。完全不定期発行の上に、それほどの時間差配本だったから、表紙に「目に止まった日が発行日」と開き直っていれたら行く先々の書店でゲラゲラ笑われた。その時の配本は気分も良く疲れなかった。不思議なものだ。
その後も調子に乗って「毎回突然発行 次号不言実行」と奥付に入れた。書店の人には「おかしな版元だな」と頭の隅っこに留まっていったようだった。
書店からの注文もおかしかった。
渋谷東急ハンズ7階のKさんは「○号を特大、○号と○号を大、○号は中」というものだった。私が目一杯持てる部数(240冊くらい)の中で、バックナンバーの部数を勝手に調節するのだ。
横浜有隣堂西口店のMさんのところもそうだった。4カ月ぶりの新刊ができたので電話すると「ええっ? もうできたのお? じゃあねえ、いつものように持てるだけ持ってきてよ。バックナンバー全然ないよ。ニコリさん売る気ないんだもんなあ。適当にみつくろって持ってくればあ」と言われ、いつも刺身の盛り合わせのように適当にみつくろって出かけて行くのだった。
補充のときは夕方の仕事(印刷会社のサラリーマン)が終わると、私の仕事机の周りに積んであるニコリを、うんこらせと持てるだけ持って、とりあえず会社を出る。
そのときの気分で行く店を決める。浜松町(印刷会社の最寄り駅)から京浜東北線に乗り、横浜で降り、有隣堂の西口と東口で納本するが、もっと回りたいので少し残し、京浜東北線で今度は全く逆の大宮に行く。そこの中央デパートにあるキディランドに全部納めようとすると、あれま、売れ残っているではないか。全部納めることができず、手元に50冊残ってしまい、重くて持っているのが嫌だからと、近くの書店に入り、「こんな本なんですけれどお願いしまあす」と言ってOKしてくれたのが、押田謙文堂のOさんだ。こんなふうにして出張馬房を開拓したりもした。最新号ではなく、歯抜けのバックナンバーから取り引き開始、ということも堂々とあったのだった。
私の女房も馬房の開拓を手伝ってくれた。
ある日中野区のN書店に集金に行ったら「あなたがご主人?」と言われた。
「は? はい」
「そうだろうなあ。あの人が奥さんだろ? 娘さんの手を引いておいてくれってくるからさあ。断われないよなあ。でもさ、こういう手作りの雑誌って久しぶりだなあ。最初はみんな自分たちでつくって自分たちで歩くっきゃないものなあ。たいへんだよなあ。それでさ、ちょっと売れると広告取って、取次を通してってなっていくんだぜ」
「はあ、そうなんですかあ」
「あなたも考えてんだろ」
「いや、全然」
「ま、売れてから考えればいいやな。で、いくら払えばいいの?」
「1568円です」
話好きなご主人であった。広告を載せることは全く考えていなかった。頭を下げるのやだもん。